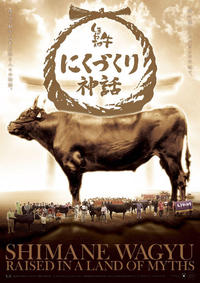イチゴ花芽検鏡実習
2018.09.24
9月上中旬は、イチゴの花芽分化状況を確認し、定植時期を決める大事な時期です。県内では各地域でイチゴの栽培が行われているため、この時期は生産者・JAから苗が持ち込まれ、普及員は花芽検鏡を行って定植時期や当面の管理についてアドバイスすることを求められます。
このたび、経験年数の短い普及員に技術を習得してもらうため、栽培研究部野菜科の協力を得て、イチゴ花芽検鏡の実習を行いました。
参加者はイチゴ担当の研究員から今年の苗の生育状況について、ほ場を見ながら説明を受けた(写真1)後、検鏡の手順について解説を受けながらテレビ画面で確認し(写真2)、実際の作業に取り組みました(写真3)。

写真1:野菜科 金森専門研究員の案内で、育苗ほ場で苗の生育を確認します

写真2:検鏡の手順について、実際の作業を見ながら解説を受けます

写真3:最後に実習。実体顕微鏡を見ながら、生長点を包んでいる葉を1枚1枚取り除いていきます
皆さん最初はおそるおそるでしたが、数をこなすうちに徐々に作業に慣れていきました。今回の検鏡では、すべての株でまだ花芽分化していなかったため、生長点も小さく難しい作業だったと思われますが、上手に最後まで葉を取り除くことができた参加者もいました!
研修の後、参加者からは、今後の普及活動の参考になった、数多く練習をできてよかったとの感想をもらいました。
引き続き研究部門の協力も得ながら、若手普及員の技術習得の手助けをしていきます。